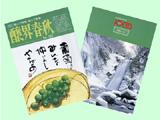IMA コラム
「ル・コルビジェ展」によせて
 現在六本木ヒルズ森タワーの最上階の美術館で「ル・コルビジェ展」が開催されています。彼は1887年スイスのラ・ショー・ド・フォンに生を受け、今年で120年を迎えそれを記念しての開催です。先日この展覧会を訪れユニテ・ダビタシオンの住戸実大模型などを体験できましたが、たまたま一昨年マルセイユのこの建物を訪れたのでその印象とともに紹介します。
現在六本木ヒルズ森タワーの最上階の美術館で「ル・コルビジェ展」が開催されています。彼は1887年スイスのラ・ショー・ド・フォンに生を受け、今年で120年を迎えそれを記念しての開催です。先日この展覧会を訪れユニテ・ダビタシオンの住戸実大模型などを体験できましたが、たまたま一昨年マルセイユのこの建物を訪れたのでその印象とともに紹介します。 マルセイユの旧港から東へ車で30分ほど走らせると、木々に囲まれて白亜の高層住宅が見えてきます。遠くから白く見えたその姿は、近づくにつれてその壁面内側が様々な色で彩られていることがわかります。車を降りると芝生の上にピロティを持ち上げる巨大な柱が迎えてくれます。1952年の竣工というから55年前の住まいですが、古さまったく感じさせません。337戸1600人が生活し、中には商店もあり、最上階には幼稚園、屋上には野外劇場やプールなどもそろっていてひとつの町といった感じです。
マルセイユの旧港から東へ車で30分ほど走らせると、木々に囲まれて白亜の高層住宅が見えてきます。遠くから白く見えたその姿は、近づくにつれてその壁面内側が様々な色で彩られていることがわかります。車を降りると芝生の上にピロティを持ち上げる巨大な柱が迎えてくれます。1952年の竣工というから55年前の住まいですが、古さまったく感じさせません。337戸1600人が生活し、中には商店もあり、最上階には幼稚園、屋上には野外劇場やプールなどもそろっていてひとつの町といった感じです。
建築雑誌への掲載(広報師)


 特別養護老人ホーム「シェ・モア」が竣工して建築雑誌「近代建築」3月号のシニア特集に掲載されました。2006年4月号の美術館特集では足立区の「千住金属工業本社ビル」が取り上げられています。
特別養護老人ホーム「シェ・モア」が竣工して建築雑誌「近代建築」3月号のシニア特集に掲載されました。2006年4月号の美術館特集では足立区の「千住金属工業本社ビル」が取り上げられています。
建築雑誌に掲載するには初めに依頼があり、その後文章・写真・図面等を揃えて何回も打合せるなど様々な準備に追われます。
文章も意匠、構造、設備、施工と分担されるのでそれをまとめる担当者も大変ですが、それらを乗り切って雑誌として店頭に並ぶのを見るのは、苦労が多かった分感慨ひとしおではないでしょうか。
ネットの普及により印刷媒体の価値が薄れているとはいえ今なお本の価値はあなどれません。先日も電話で「あのビルはどこかの雑誌に載っていますか?」等の問い合わせもあり、当事務所でも「新建築」「日経アーキテクチュア」誌から企業の広報誌に至るまで、当社作品が掲載されたリストを作成してこのような問い合わせに対処しています。
いわば設計業務の「後方支援」として。
(広報師)
「醸造蔵」設計譚
忘年会の季節となり酒に親しむ機会が多くなる年末にちなんだ話題を一つ。世間には様々な専門分野の雑誌があり、ここで紹介する「醸界春秋」は神戸市灘にある雑誌社が発行する酒専門の月刊誌です。酒にまつわる情報やエッセイ、研究などを紹介し現在112号を数える「飲んで酔境、読んで教養」というバラエティー豊かな雑誌です。
その中に「醸造家と建築」という題名で神戸女学院大学の川島智生(ともお)先生が連載を続けています。古来、町の中で大工の棟梁により創り続けられていた酒蔵と、酒造メーカーが建築する近代的な酒造工場のはざまにあって、建築史的に取り上げられることが少なかった「醸造蔵」にスポットを当ててその系譜を丹念に読み解いている建築史家です。
免震ことはじめ
 鎌倉大仏の寺として知られる長谷の高徳院は、本堂、回廊、客殿の設計を担当した当事務所ゆかりの寺です。あまり知られていないことですが、その大仏は昭和36年(1961)に大改修が行われました。
鎌倉大仏の寺として知られる長谷の高徳院は、本堂、回廊、客殿の設計を担当した当事務所ゆかりの寺です。あまり知られていないことですが、その大仏は昭和36年(1961)に大改修が行われました。
建長4年(1452)に建造が開始され、室町時代の大津波で大仏殿が流されて以来露座となった大仏(阿弥陀如来坐像)は高さ12.3m総重量121トンの金剛坐像です。大正12年(1923)年には関東大震災を受け、頭と頸の部分にクラックが入りさらに大地震が来れば倒壊の恐れがありました。そこで1961年当時の文部省文化財保護委員会(関野克博士)より、法隆寺・法輪寺などの収蔵庫の設計を行っていた当事務所に設計の依頼がありました。
「都市に歴史」
8月30日都庁にて夜までの会議を終え外に出ると、庁舎が五色の照明で彩られていました。この日の夕方オリンピック誘致の国内候補地が東京に決定されたとのことでした。計画ではメインスタジアムを晴海に、その周辺に選手村やプレスセンターをつくるもので、TVの画面からも昭和36年の東京オリンピックを懐かしみ、期待する声が多いようでした。
実はその遥か前に東京で「幻のオリンピック」そして「幻の万国博覧会」があったことを知る人は少ないでしょう。昭和15(1940)年の皇紀紀元2600年を祝う万国博覧会が計画され、会場には昭和初期に埋め立てられた月島(現在の晴海・豊洲)と横浜が選ばれました。東京では地下鉄の延伸が計画され、勝鬨橋も完成を迎えようとしていた頃です。
一方、第12回オリンピックは昭和11年のベルリン会議で決定され、東京市はそれを受けて臨時建築部を設け現在の駒沢公園をはじめとすると市内に競技施設を設計しました。この時、選手村担当となったのが東京帝大建築学科を卒業したばかりの入江雄太郎でした。
心に残った言葉(ある会長編)
建築設計に携わっていると、仕事を通じて、世界で活躍する企業のトップと接する機会があります。僕も数年前、ある環境配慮型の製品で世界的にシェアをもつ会社の、本社ビル設計監理の中で、その会社の会長とお話しする機会が度々ありました。竣工間近の頃、会長から、エレベーターホールのロールスクリーンにある文字を筆入れしたいとの要望があり、その言葉は「本来無東西」。秘書の方にその意味をうかがうと、自分で考えることに意義があるのだよ、との返事で、含蓄ある切り返し。
考えました。「ホンライ、トウザイナシ」。東西南北なんて概念は、人が作った形式にすぎない。それにとらわれることはないのだよ。形や既成概念にとらわれない、自由奔放な発想力を持ちなさい。そんな意味でしょうか。
経験と実績に裏打ちされた格言。どんな本を読むよりも心に染みます。
-Canna-